
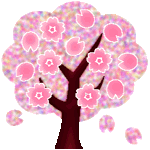 桜と向陽小学校
桜と向陽小学校
| 今月の語り部は、すすきの町にお住まいの奥山康さんです。 奥山さんは昭和23年から昭和40年まで向陽小学校で先生をしておられました。向陽小学校の校庭には毎年春に桜が見事に咲きます。この桜のことや向陽小学校ができた頃のことを教えていただきました。 当時は地域の人がとても協力しあって、子ども達や学校を大切にしていたことがよくわかり、感動すら覚えました。 |
 |
|||
 現在の相模原米軍補給廠 |
向陽小学校は昭和23年5月16日に旭第二小学校として、造兵廠(今の相模原米軍補給廠)の中に独立開校しました。造兵廠の西側フェンス横の下り坂の途中に正門がありました。そこに造兵廠女子の宿舎、女子寮が並んでいました。そのうちの2棟に移転し、翌年には70名の卒業生を送り出しました。 そして、昭和26年に旭第二小学校は向陽小学校と改称されました。当時の児童数は500人ほどだったということです。 |
| 昭和28年に米軍基地の拡張のため、現在の向陽町に新築移転してきました。私も移転に参加しました。机や椅子などは自分達で運びました。 当時は物も食糧もあまり無い戦後の混乱期で大変でしたが、地域の人々が向陽小学校を移転するために、積極的に協力してくれました。向陽小学校の敷地はもともと畑でしたが、宮下の農家の人たちが無償で提供してくれました。 また、グラウンドは元が畑でしたから、雨が降るとぬかるんで靴が埋まるほどでした。そこで、米軍が基地で炊いた大量の石炭ガラをブルドーザーで運んで来て敷いてくれました。この作業にも地域の人たちは、それぞれの仕事があるにもかかわらず、協力してくれました。 移転当時は校舎は木造でしたが、その後新築して現在の校舎になりました。 |
 校庭と林 |
 今年の桜 |
植木はイチョウ、桜など、造兵廠の中にあったものを地域の人たちが担いで運んだり、米軍が重機で運んだりして移殖しました。 校庭の横の林もすべて移植したものです。清新小学校や内山緑化から植木を分けてもらい、地区の人たちが協力して運んで移植されました。かなりたいへんな作業で、長く工事をしていました。 |
| 体育館は後(昭和33年)からできました。それまでは、2教室ぶち抜きの教室があり、仕切りを取りはらって広くして、学芸会・音楽会などをやりました。 遠足は春と秋の年2回ありました。小山の長池公園にはよく行きました。また、今は開発されて無くなってしまいましたが、津久井の発電所にも行きました。春のつつじがすごくきれいでした。 修学旅行は日光に行きました。文化遺産を体験させることが大事だというわけで選びました。 運動会も春の小運動会と秋の大運動会の年2回ありました。小運動会は、1年生が入ったばかりですぐにはできないので幼稚園の延長程度でできる競技をしました。現在、秋の運動会のことを大運動会というのは、この小運動会があった頃の呼び方のなごりです。 |
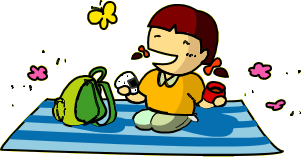 |
| 当時は給食はなく弁当でした。食糧事情が悪く、お弁当を持ってこられない子どももいました。弁当を持ってこられず校庭の隅で遊んでいる姿は、哀しいものでした。担任の弁当を分けてあげたいけれど、担任も食事抜きではどうすることもできずもどかしい気持ちでした。 給食が始まるとそういうこともなくなり、子ども達も元気にお昼を過ごしていました。 |
 |
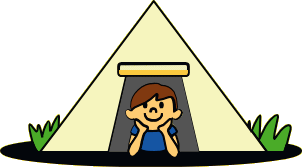 |
6年生の夏のキャンプは市内で初めて向陽小学校が行いました。最初の夏には、横浜、真門小学校の教室を借りて一泊のキャンプをし、海で泳ぎました。飯ごう炊飯もしました。バスを借りきって行きましたが、横浜は遠くてたいへんでしたので、2年後から津久井、青山の浄水池で行うようになりました。浄水場のご好意で水を引きプールのようにしてもらいキャンプをしました。 青山のキャンプ場へはトラックなどの確保は大変でしたので、大八車に荷物を積んで、これも地域の人が運んで行きました。ほんとにたいへんでしたが、皆子どもたちのために協力していました。子どもたちはバスで行きました。 市内の他の小学校も見学にくるなどして、そのうちそれぞれでキャンプをするようになりました。 |
 |
雪が降ると、職員が朝早く来て学校の雪かきをし、登校してくる子ども達のために道を作ってやりました。高学年の子は面倒見がよく低学年の子を気をつけてやりながら、登校していました。 教室の暖房は、移転当初は教室の真中に1メートル四方の木枠の火鉢があり炭火で温めました。ほとんど温まりませんでした。朝、用務員さんが炭をおこして準備してくれました。でも、炭も大事なので、火鉢を使うのは朝だけでした。雪の朝など、高学年の子が低学年の子を火鉢のそばに連れて行って、火にあたらせていました。 ストーブは昭和28年に入りました。だるまストーブでした。 |