

 小山の名物〜禅寺丸(ぜんじまる)柿
小山の名物〜禅寺丸(ぜんじまる)柿
| 今年最後を飾る話題は、小山の隠れた名物「禅寺丸柿」です。柿に「禅寺丸柿」という種類があることをご存知ですか?この柿は、150年以上もの昔に、由緒正しい柿生の甘柿が小山に根付き、この土地の人に愛されてきました。歴史を感じさせるこの柿のことを宮下本町2丁目の原弘さんにお聞きしました。 |  原 弘さん |
||
| 今から約800年前の鎌倉時代に、現在の川崎市の王禅寺というお寺の山中から、甘柿が偶然発見されました。この柿は「禅寺丸柿」と呼ばれ、日本最古の甘柿といわれています。江戸時代、「禅寺丸柿」は人気の水菓子としてもてはやされ、明治時代には明治天皇にも献上されました。 現在の「柿生」は、明治時代に「柿の産すこぶる多いため」として「柿生村」となったと記されています。「禅寺丸柿」は富有柿と違い、全体的に小粒で丸く、甘味も淡い、不完全甘柿と言えます。枝を切った後になる柿は、何年かは渋いそうです。しばらくしてから、甘くなる性質があります。 川崎市麻生区には柿生禅寺丸柿保存会があり、地元名産として「禅寺丸柿ワイン」を作り、売り出しています。保存会では、柿の木を守る活動と増やす活動をしており、苗木を配布しています。また、JA全農かながわ通信には、かながわブランド「禅寺丸ワイン」が紹介されています。柿生では、なり年に年間6トンの「禅寺丸柿」が生産され「禅寺丸柿ワイン」が作られています。 |
|
| 小山の禅寺丸柿 |
|
| 小山地区の道を歩いていると、あちらにもこちらにも禅寺丸柿の木を見つけることができます。宮下本町2丁目界隈には、調べただけでも推定樹齢150年の「禅寺丸柿」の大木が50本ほどあります。小山地区全体ではまだまだ相当の数の禅寺丸柿があると思われます。 宮下本町にお住まいの原弘さんのお宅には、屋敷内に2本の「禅寺丸柿」の大木があります。推定樹齢150年で、根元の幹回り160cmと180cmです。地上から120cmの高さで接木されています。台木から出た枝は後に切断されたもので、切断跡は樹皮で完全に覆われています。その凹んだ部分に、宿木の紫式部が出ていました。家を建て替える前には、4本の「禅寺丸柿」があったそうです。「禅寺丸柿」の根元には、屋敷の神のお稲荷様が建てられています。伏見稲荷神社から分けてもらったお稲荷様のお札が安置されているそうです。今では、「禅寺丸柿」も共に守っている屋敷神です。 昔のように、服の袖口を、鼻汁でテカテカにしたガキ大将が、長い棒の先で柿を盗む光景は殆ど見られなくなり、冬が近づいても「禅寺丸柿」を食べるのはカラスだけのようです。関口武雄さんの「柿盗り物語」がやけに懐かしく感じられるこの頃です。 (小山の昔語り11月を参照してください) 「禅寺丸柿」は、明治の初頭より、小山村・現代の宮下本町をずっと見守り続けて、戦中戦後の食糧難の時代には、庶民の胃袋を満たしてくれた貴重な存在でもあります。最盛期には、今の倍すなわち100本もの「禅寺丸柿」がたわわに実り、干し柿などに加工したものと推定されます。小山の柿の文化をまざまざと知らされる想いがしました。 |
原弘さん宅の2本の禅寺丸柿  根本にはお稲荷様  柿もぎの道具 |
  |
小山にある禅寺丸柿の分布を調べて地図に示しました。宮下本町2丁目を中心に54本ほどありました。 | |
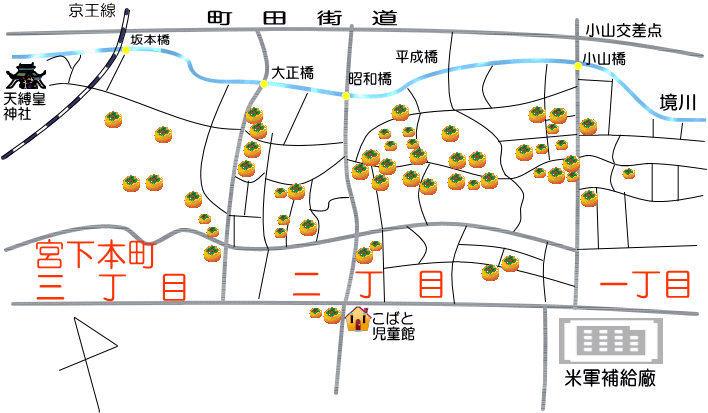 |
||