

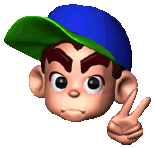 わんぱく小僧の思い出の味
わんぱく小僧の思い出の味
| 関口武雄さんの紹介 今月の語り部は、11月に登場しました関口武雄さんです。 昭和初期の小山・現在の宮下本町界隈には100戸ほどの農家があり、蛇行して流れる境川流域は桑畑でした。その他の地域は殆どが山林や原野でした。学校は小学校2年生までは宮下の旭小第2分校で、3年生からは橋本の旭小まで1里の山道を歩いて通いました。その通学路で野山の木の実などあさって食べ歩いた懐かしいむかしのお話です。 |
 関口武雄さん |
||
| 春先 |
|
 ちがや  やまぼけ(しどめ)  どどめ |
【ちがやのつぼみ】 ちがやは草丈50cm程で、茅に似ているが、株にならず1本1本生えています。春先に芽生えて、夏に穂が出て白い綿のようになります。穂が出る前の膨らんだ時、穂になる芯を引き抜いてしゃぶりました。噛んで汁を吸ってからほきだしました。味はほのかに甘く淡白なものでした。 【しどめ】 しどめは山ボケの実のことで、早春に花が咲き、やがて実になる6月頃、まだ青い実をもいで食べました。すっぱい味でした。子どもが遊び半分で食べるものでした。 【どどめ】 どどめは桑の実のことで、白から薄黄緑、やがて赤みがかって6月ごろに、紫または黒色になって熟れました。甘くて美味しかったものです。もいだ手や食べた口の周りが紫色に染まりました。どどめを摘んで竹筒に入れ、棒で突いて、桑の実ジュースもどきを作って飲みました。霧生さんの屋敷に大きな桑の木があり、みんなで登って桑の実を採って食べました。いまでもかろうじて古木が残っています。 |
| 【いたどり】 6月頃、川の土手などに生え、葉が赤く、出始めは軸が太くアスパラに似ています。茎は中空で、なるべく太いものを折り取って、皮をむいて食べました。根元の方から皮をむくと、するっと一気にむけました。すっぱくて少ししか食べられません。皮をむいて塩漬けにすると、すっぱさが薄れて少しは食べられます。今では、出始めのころ、芽や葉を摘んで、山菜てんぷらにして出している旅館もあリます。いたどりは草丈が1.5mほどになり、細かい白い花が咲きます。枯れると太い軸の根元の中空に虫がいることがあります。この虫は魚釣りの餌になりました。 【ぐみ】 6月頃、真っ赤でちょうちんの形をしたぐみは太さが5mm、長さが1cmにも満たないが甘くてみずみずしくおいしいものでした。たわらぐみは俵の形で、指先くらいの大きさで熟れると橙色になりました。甘ずっぱくて少ししぶい味がしました。近くの長谷川さんの屋敷に大きなたわらぐみの木があり、よく食べました。その大木は今でも残っています。 【ぼたんきゅう】 当時は珍しい「ぼたんきゅう」は、原清兵衛さんの家の横に大きな木があり、たくさんなっていました。学校帰りに石を投げて実を落として食べました。甘くすっぱくて美味しかった記憶があリます。 原清兵衛さん自宅前にバス通りはなく(昭和17年または18年に軍が作ったそうです。)数十メートル横浜線側にせまい道路があり、清兵衛さんの屋敷はその場所の奥まったところにありました。その辺りは当時、広大な梅林でした。学校で、「青梅は毒だから食べるな」と言われていましたが、かまわず食べた記憶があります。その中には、ぼたんきゅうの木もありました。 ※ぼたんきゅうとは、「はたんきょう」(巴旦杏)のことかと思われます。 |
 長谷川さんの屋敷にあるたわらぐみの大木  梅の写真です |