
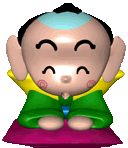 千人同心、天縛皇神社
千人同心、天縛皇神社
| 久保田昇さんの紹介 今月の語り部は、久保田昇さんです。現在は、こばと児童館の館長さんです。次の世代に、小山の昔を知って貰いたい。それが私たちの世代の役割だという気持ちで、インタビューに応じて頂きました。 |
 久保田昇さん |
||
| 久保田家の先祖は武田家の家臣だった |
|
 |
【久保田家の先祖】 江戸時代の初め、甲斐武田家の家臣たちは住みなれた甲斐の国を離れて、津久井、八王子を経て小山村に移り住んできました。愛川や厚木方面に住んだ人たちも多いようです。私の家(久保田)は有名ではありませんが、八王子千人同心の組頭の一人で萩原某の弟が現在の町田市に分家し{境川翁萩原四郎兵衛}と呼ばれ、当時暴れ川と言われた境川の改修工事などに尽力し、台風による大水の被害を防いだと言われています。翁の墓は福生寺の境内にあります。平成橋近くの町田側にある長屋門や主屋の立派な{萩原大尽}と呼ばれた家は一族です。 |
|
【千人同心】 |
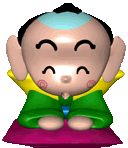 |
|
【天縛皇神社】 参考文献 「新編相模国風土記稿」 |
 天縛皇神社  天縛皇神社の神輿飾りと伝えられる  蓮乗院本堂 |