
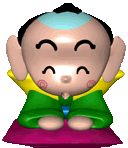 小山の子どもの生活-Part1
小山の子どもの生活-Part1
| 今月の語り部は現在、小山地区青少年健全育成協議会会長をしておられる坂内ツナ子さんです。坂内さんの御実家は養麟学舎に関係のある霧生家です。実はそのお話を聞きにうかがったのですが、坂内さんが語ってくださった昔の子ども達の話がとてもおもしろく、こちらを記事にするべーということになりました。なかでも子どもの叱り方叱られ方は、坂内さんの語り口調もあって、妙に感心させられました。 |  坂内ツナ子さん |
||
   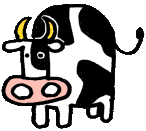 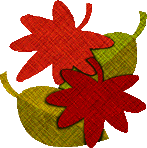 |
(注)ここの記載については、語り手坂内さんの実際のお話しを、出来るだけ忠実に表現させていただきました。 1.子どもたちの遊び、楽しみ このあたりはお蚕が盛んだったので山と桑畑でした。木がいっぱいで、蝉なんかをとっていました。蝉をとるには、梅の枝を丸めて、蜘蛛の巣をくるくるくっつけて網にしました。農家の軒先には、蜘蛛の巣がいっぱいありました。だから子供の遊びは、全然不自由しませんでした。今の子供は冒険するところが無くてかわいそうです。多摩境に向かっていく途中の山は、段々のたんぼになっていてえびがにもいました。「あばば」(茶色で斑点があり、どじょうの様なものなまずの小さい感じ)もいたし、「はや」や「からみっちょ」(あかいとかげ、おなかがどぎついくらい赤い)もいました。 お菓子は、遠足の時、上溝の商店街まで父が買い物に行きました。家は、子供が7人いました。遠足の度に、せんべい2枚、あめいくつと、子供達に分けてくれました。遠足はそういう喜びがありました。キャラメル1個貰うにも達成感がありました。今は物が豊富だからシメシメとか気持ちの高ぶりも無い。がっかりすることもない。難を逃れる工夫も無い。昔は四六時中ありました。 2.ことばと方言の話 私は昔からここに住んでいたので、すごい言葉を使っていました。母と話すと、「おめーよ。よっていきなよー。」、むこうのこっちのあっちのという話し方でした。(そこでどんな方言があるのか教えていただきました。) 『つっぺった、おっぺした』 リヤカーがあぜ道を通っていて、土砂みたいなところにおちて動かなくなると、「おめーよーはやくはやく来てくれよー。リヤカーが動きゃーしねーよ。つっぺしちゃってよー。はやくおっぺしてくれよー。(押してくれよの意)」 『ひっかけまわす、おっかけまわす』 ひっかきまわす事 『こば』 テーブルの角のようなところ 『ひののき』 「今ツナ子は何やっているんだよ。そういうことはひののきにやるもんだ今そんなことやんないで」これは、電気をつけて勉強しているときなど「電気代がもったいないから、そういうことは、日のあるうちにやりなさい」の意味。 『そらっこと』 例えば、みんなが小豆の枝をゆがいている間に遊んでいたりすると「何やってんだよー、そらっことばかりやって、はやくやっちまいな」「まーたそらっことばかりやってんだよー」皆がやっているのに、自分だけやっていないこと。子供会などで「ほらーほらー。そらっことばかりやって」と言うから、そらっことのおばさんと言われています。 |