
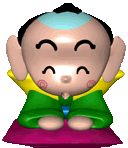 小山の子どもの生活-Part2
小山の子どもの生活-Part2
| 今月の語り部は先月に引き続き坂内ツナ子さんです。生き生きした語り口調で昔の子どもと大人の様子を伝えてくれました。 (注)このコーナーの記載については、語り手坂内さんの実際のお話しを、出来るだけ忠実に表現させていただきました |
 坂内ツナ子さん |
||
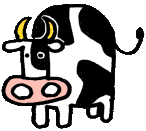 牧場の話 牧場の話 |
|
  |
三菱の脇が、東洋無線で今はニフコになっています。昔、霧生牧場、田野倉牧場の二つがありました。雪印乳業に牛乳を出していました。霧生牧場は、ここでは、放牧では無く、牛小屋形式でした。家のまわりに、やぎ小屋、豚小屋、牛小屋、全部ぐるーと回っていました。鶏を最後にやって病気になり、私が高校に入ったくらいの時、兄が不動産屋になりました。その後、昭和37年にメッキ屋に転業しました。牛をやっていた頃は、小中学校だったので、毎日親の手伝いをやりました。 それから賞味期限の面白い話。2年に1回、森永乳業から農協を通じて、トラック1台、カマスに入れてお菓子がきました。こんぺいとうとか英字ビスケットなど昔のお菓子がいっぱいありました。お菓子は賞味期限が切れたものばかり。向こうは向こうで始末するのに困っていました。今のリサイクルみたいなもので、牛には賞味期限は関係無いから、それをすくって牛にあげます。ふすまとかわらとかお菓子を混ぜて与えるとおいしい乳がいっぱい出ました。 今日お菓子が来たというと近所の人たちがザルを持ってきました。「今のうちにとっておきなー。なくなってしまうからよー。」 カマスを逆さまにしてほじって、金平糖のようなカマスの中で傷まないものを取って、グチュグチュになっているものはザルに入れました。 |
| 昔の子どものしかり方、しかられ方 |
|
くすねるという言葉知っている?人の目をごまかす事。人の見ていない時、くすねる。「何でそんなものを口に入れて。早く出しな。」と言われておせんべいとか出すと、「これまちな。」仏壇へ行って、「ちょっとまちな」お線香をつけて、「ツナ子は頭はオリコーなんだよ。だけどこの手が悪いんだよ」と言って手をチュッチュッとやられる。もっと悪いことすると、この中に悪い虫がいるんだよと言って手をつねられる。親は頭を叩かないで、手を叩いた。足で何か悪さをしたら足を踏みつけられた。同じことをしっかりしないで適当にやると、やる気があるのか無いのかとお尻を箒で叩かれました。やる気があるのかバンッ、無いのかバンッ、どっちだバンッと3回やられました。ないと言ったらもっと怒れらました。「先祖に申しわけ無い」と言って、大黒柱にしばりつけられました。昔の親の方が根性がありました。 お客さんが来るとおせんべいとかお菓子が出ます。子供の分はありません。母や父が一緒にしゃべっているところを後ろからくすねると、親はお客さんに対応しながらピシャッとやる。手の皮の寸前のところをチュッツとつねられると、皮が切れました。昔は、お菓子は、月に1回食べられるかどうかで、お客さんが残してくれたら貰えました。残せー!!お菓子が残っている時、お客さんが早く帰らないかなーと障子の間から待っていると、母は、人にくれるのが好きだから「あーこれ持って行きなさい」と持たせました。残念!!まただよー。 「たまみつ」て知ってる?サッカリンのことで、丸い錠剤で、砂糖より甘く人工的に出来ていて、赤い箱に入っていました。小さい薬と同じ。砂糖の代わりに使っていました。砂糖を使うとお金がかかるので、「たまみつ」を入れる。「たまみつ」2つのうちの1個をくすねる。2粒入れるんだよーと言っておいて口裏に1個入れる。すると、この手が!ピシッとなる。 昔は、お百姓の家だから、15人とか20人とか住んでいるので、とにかく寝泊りするところがあります。夕方早く帰らないと、家に入れて貰えません。味噌小屋とか山羊小屋とかハイヤ※とか、室(むろ)とか小屋がある。8時になっても帰って来ないと、母が探します。こっちは味噌小屋の樽の陰とか山羊小屋とかに隠れている。しょうがないや。そのうち出てくるべーとほっとかれる。そうするとタケ叔母さん達が、かわいそうと言って探してくれました。15人くらいの生活していると、叱るおじさんが居ても助けてくれる叔母さんが居たりしました。 ※ハイヤ 納屋で大きな一軒屋。穀物や家畜用の藁をしまう場所だった。 |
 |
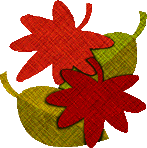 |
このあたり(坂内さんのお宅があるすすきの地区)は、かつらこぶという山でした。今は削っているからなだらかですが、当時は平らにしきれないからもっと高くて急な坂でした。こんな坂道を弟と二人でリヤカーにおかぶを積んで運びました。昔は今の「子供の人権」以前の問題で、子どもは道具のひとつでした。でもそうやって子どもは生きる知恵を学んでいきました。だから子供はもっと使った方がいい。 小学校5、6年生でお手伝いするのがあたりまえでした。結婚式とか葬式があると関口みちひこさんの家の前に倉があり、お皿とかお膳や茶碗などがあります。お膳50脚、おわん60個、茶碗いくつとメモしたものを持ってリヤカーに積んで自分の家に持ってくる。母とかおばさん達を手伝って食器を水洗いして乾して縁側に積む。母が数えて、あれが足りないぞと取りに行き、それが終わるとそうざいの準備をする。畑に行ってじゃがいもを掘ってきたり、茗荷を取ってきたりする。お吸い物に茗荷をザル一杯井戸のところできれいに剥く。ザル一杯剥くと倒れることがある。じゃがいもは爪でカリカリ剥く。文句も言わず「母ちゃん剥いたよー。何したよー」と言って。次は薪の準備をする。そんな具合です。 |
くわでっぽね(桑出骨?)は、知っている? 蚕にやる桑の木の枝を捨てないで束ねたもの。つけんぱって知っている?桧みたいで、着火剤、マッチみたいなもの。木を細くさいて頭に緑の硫黄をつけたもの。昔はオリンピックの聖火の様に絶対にいろりの火を消さないでおいたから、いろりで火の上に灰をかぶせておいて、つけんぱを持っていき、火をぽっとつける。そして桑出骨に火をつける。そうすると燃える。次に、薪をくべる。桑の木は、軒に乾してあるからすぐ燃える。これは貴重でした。 |
 |