
![]() �q�ǂ���A���z�ۓJ���̘b
�q�ǂ���A���z�ۓJ���̘b
| �@����́A�������̂ɂ��Z�܂��̓c���m�q��������K�˂��܂����B�c������́A���a16�N�A���{�̈������w�Z�ɏ��q�����Ƃ��Č}�����܂����B20����11�N�����w�Z�ɋ߂��A�펞���̑a�J�����Ƃ̊ւ��ȂǖY����Ȃ��̌�������܂����B�܂��q�ǂ������ۓJ���ݗ��ȂǁA���N���R�n��̎q�ǂ��B�̋��犈���Ɍg���ė����܂����B���N�Ď����}������c�����q�ǂ��������������������Ȃ́A���[�~���}�}�ł��B�����́A�펞���̎v���o�⏬�R�n��q�ǂ���̐ݗ��A���z�ۓJ���̐ݗ��ȂǁA�����̏��f���܂����B |
 �c���m�q���� |
||
 �s�q�A�����݂͂玏 |
�@�@���͌��s�̎q�ǂ���́A�w�Z�g�D�Ƃ͖��W�ɒn��̎q�ǂ��琬���ƂƂ��đ��̓s�s�Ƃ͈ꖡ��������̂Ƃ��āA�X�^�[�g���܂����B�ǂ̗l�ɂ��Ăł��������f���܂����B�܂��A���w�Z�̐搶�B���ϋɓI�Ɋ������x���Ă�������b���Ē����܂����B �@���z���w�Z�̏���Z���́A�эZ���搶�ł����B�эZ���搶����ԋC���������Ƃ́A���l�̒c�n�ȂǓs��痈�Ă���q�ǂ������ƒn���̓c�ɂ̎q�ǂ������𒇗ǂ������邱�Ƃł����B���̂��ߍZ�O�w���ɗ͂����A���N�w�������x��������܂����B���N�w�����́A���A�s���2�N�ԈϏ����ꂽ���Z���w���ɂ������Ă��܂����B�����A���N�w�����Ƃ���2�l�h�����Ă��炢�܂����B �������A2�l�����ł́A�n��S����������Ȃ��̂Ŋe�n��Ɏq�ǂ���݂����Ȃ��̂��������ǂ����Ƃ������ƂŗэZ���搶���l���܂����B�e�O���[�v60�����炢�Łc�B�܂��{�������x60�l�A�������̂͐l���������A�������̏�Ƃ������̉��ɕ����܂����B���̑��́A���R����i��ɎR�т��q�ǂ���ɉ��́j�A����Ɖw�O�i�w�̎�O�j���琴�V�{���̕ӂ�ɂ������ȃO���[�v�i��̐��V�Ђ܂��q�ǂ���j���ł��܂����B �o�s�`�n�抈���Ƃ͕ʂɕی�҂�2�l���A�Z�O�̎w�����Ƃ��ďW�߁A�ċx�݂͂ǂ����悤�Ƃ��A�������n�߂��̂��q�ǂ���̎n�܂�ł����B���̍��́A�w�Z�̐搶���Z�O�w���ɐϋɓI�ɂ�������Ă��܂����B ���a38�N�`48�N�̊ԂɑS�s�ɌĂт���100�ȏ�̎q�ǂ���ł��܂����B���Ԃ̈琬��ł���A�s�̐E��������Ă����ł͖����̂ŁA���ނ��o������A��t��������A�s���������肷��̂�����Ȃ��Ă��܂����B����Ŋe�����قɂ��˂������Ēn��q�A�����܂����B�s����14�n��q�A���o���āA�s�q�A����������܂����B |
| �q�ǂ���ł͂ǂ�Ȋ����������� |
|
| �@�@�싅���ŏ��Ɏn�߂܂����B�������s���܂����B�ŏ��͎s�S�̂�11�`�[�����炢�B��a�̍�����肽���̃v�[���̌��������ɖ싅�ꂪ����܂����B�l�b�g������܂���B�J���~������ʂ����ŏo���܂���ł����B���K�͊w�Z�ōs���܂����B �@���̌�n�߂��̂����̎q�̂��߂̃h�b�W�{�[���B��1��́A�s�̑̈�Ղōs���܂����B���a48�N�̑��ł́A�k����4�u���b�N�ŏ��R�n�悪�A�D����Ɛ肵�܂����B �@ �@�̈�I�Ȃ��̂͐���ł������A�����I�Ȃ��̂����Ȃ��̂ł͂Ȃ����Ƃ������ƂŁA�q�ǂ���̏��݂�Ȃɒm�点�悤�ƁA�P�N�̊������܂Ƃ߂Ďq�ǂ���V���ɂ̂����肵�܂����B���̌�A�q�ǂ���V���R���N�[���ƂȂ��Ċ������Ă��܂��B �@�e�����܂������Ȃ��q�ǂ������邱�Ƃ��K�v���Ƃ������ƂŁA�s�̋���ψ���ɂ��肢���āA�W���j�A���[�_�[�i���w���j�̌��C���s���܂����B������50�l���炢�琬���܂����B�W���j�A���[�_�[�ƈ琬��̘A�g���͂���܂����B�e�n��̌����قŊe�q�ǂ����6�N���̒����烊�[�_�[���琬���A���w�ɍs���Ă��q�ǂ���ƘA�g�ł���l�ɂ��܂����B����ɐN�̉Ƃ�����܂����B�i���͌|�p�̉ƂƂȂ��Ă��܂��B�j�����ɖ��N���w���Ǝq�ǂ���̃��[�_�[���W�߂āA�F�B���m�ǂ�����������ǂ����ȂǁA������̐搶�ɋ����ĖႢ�܂����B�u�q�ǂ��̂��߂̎q�ǂ��ɂ��q�ǂ���v���^�c�o����l�ɂȂ�܂����B �@�q�ǂ���̊�����́A�����͊e���ŏW�߂܂����B���̌�A���Ղ���ΑK�i��������j�Ȃǂ͎q�ǂ���ɂ܂킷�ȂǁA������̉�������l�ɂȂ�܂����B�p�i����Ȃǂ��q�ǂ���ōs���܂����B���������炨�肢���܂��Ƃ����ďW�߂܂����B�g���b�N�ŏW�߂邱�Ƃ�����܂������A�댯���Ƃ������ƂŃ����J�[�ɂ��܂����B�q�ǂ������Ȃ��Ƃł����̓��́A�V���ȂǏo���Ă���܂����B �@�ċx�݂̃v�[���́A�Z�O�w���̕���e�A�搶�����Ă�������A�q�ǂ���������������Ƃ͂���܂���ł����B���A�ċx�݂Ɋw�Z�Ńv�[�����g���Ă��Ȃ��͎̂c�O�ł��傤������܂���B�e�n��Ŏq�ǂ����Ԓd�Â�����|���Ȃǂ����܂����B |
 �������̎q�ǂ���h�b�a�{�[���`�[�� �u�������̂̂���݁v���  �q�ǂ���V���R���N�[���ŗD�G�܍�i �{��2���ڎq�ǂ��� �u���R�n��q�A�L�O���v���  |
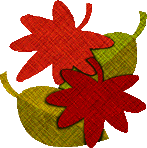 |
�@�d�����Ȃ������ŃL�����v�̘b �@��������ŃL�����v�������Ƃ�����܂��B���c�s�ׂ̗̔����q�̂�������ɍs���܂������A�d�C������܂���ł����B�s�������ǂ���Ƃ��܂����B���a40�N���ł����B���͓d�C������܂����ǂˁB���킢��ˁB���������̎q�͓��ɂˁB���ꂳ�����A��čs�����̂ł����B�낤�����͂���܂����B���̌��ł��͂������H�ׂ܂����B���Ƃ��ł��܂������ǁA�q�ǂ��B�ɂƂ��Ă��A�Y����Ȃ��v���o�ɂȂ�܂����B �A�傫�ȑ傫�ȃJ���^��� �@�s�u�Ō�����ł����A�k�̍��ł͂ˁA��̏�ŔɊG��`���ăJ���^������Ă�����ł��B�����ŁA�傫�ȃJ���^�����Ă��܂����B��ł��ł��邵�A�J�̎��͍u���ł��ł��܂��B�u�ǂ����낤�H�v�u���I�v�u�ł�48�����ׂĈ�����̂�`���̂���ς���B�v��́A�q�ǂ��B�̖����̍s���̒�����I�т܂����B�唻���炢�̌����A�Е������ŕЕ����{�[�����Ă��܂����B��߂悤���Ƃ����q�����܂������A������قɏW�܂��Ă��n�߂܂����B�V�тƂ��s���Ƃ���ʈ��S�Ȃǂ�����A1�l��1���Â��Ƒ�ςȂ̂ŁA2�l�ő��k���Ȃ���d�グ�܂����B���ɍD�]�ł����B�܂��厖�ɂƂ��Ă���܂��B |
| �ۓJ�����ł������̌o�܂��J�b |
|
| �@�����ł͊y����Ђ��Ȃ��ƌ����Ă���c�����A����̕��̉����ŌۓJ�����o�����o�܂�b���Ă���܂����B �@��l�����c�s�̏��w�Z�ɋ߂Ă���A���c�w�O�ŌۓJ�������̂����ɂ��Ȃ����ƗU���Č��ɍs���܂����B�e���w�Z50�l���炢�ł����B�u���[�ǂ��ȁB����Ă݂����ȁB�v�Ǝv���܂����B�����ł͊y����Ђ��Ȃ��̂Ɂc�B��ԐS�z�����͎̂w���҂ł��ˁB���ꂩ��A�n�悪�ǂ����f���邩�B���N�ۂ��ǂ������Ă���邩�B�w�Z�łȂ��n��ł�肽�������̂Ő��N�ۂ̉ے��ɑ��k���܂����B����������u���Ȃ����I�A���Ȃ����I����Ȃ��Ƃ��v�������́B�s�̕��Ő��N�w���琬���������邩��S�z����ȁB�v�Ɖ������Ă���܂����B �@�܂��A���K����̂ɁA�Z���̈�ق𗘗p���Ȃ���Ȃ�܂���B�w�Z�ɍs���čZ���ɑ��k���܂����B�u�S�z����ȁB�w���ł��鋳�t���ЂƂ肢���B�v�ƌ����Ă���܂����B���ʂ̎��Ƃ��I���Ă���A�S�R�ۓJ���Ȃǒm��Ȃ��q�ǂ��B���W�߂āA��肽���̂ł����B�u����͐������B�v�w�Z�łȂ��n��ł�肽���̂ł����B�u����͗��ޑ��莟�悾�B�v�ς��ς��Ƃ����̂��Ƃ��A�n��ł���������ق̕��ɂ��b������ǂ����낤�Ƃ������ŁA�q�ǂ����Z�O�w�����A���N�w�����̕����W�߂đ��k���A�ǂ�ǂ܂��Ă����܂����B��W�����炾������50�l���炢�̉��傪����܂����B���a40�N���̂��Ƃł��B���̌�A�w������搶�͎��X�ƌ�����ʼn������܂����B��1����܂�ɏo�ꂵ�����z�ۓJ���̂������́A�Y����܂���B �@ ���̍��A�ۓJ���́A�s�ł͂����������������̂ŁA�R���N�[���͂���܂���ł����B���̌�A�c���A���A�����Ƃ��ۓJ��������ɏo���A�s�Ŗ��N�R���N�[�����s����悤�ɂȂ�܂����B �@���݁A���z�ۓJ���͑��������Ȃ��Ȃ��Ă��܂����B10�l���炢�ł��B1�N��������Ă���̂�����Ɨ܂��o�Ă��܂��B�ł��琬�҂̕����M�S�ɂ���Ă��������Ă��܂��B��N���j�z�[�����V�����Ȃ�܂����B�v���o���ƁA�ݗ������͑̑����ł���Ă��܂����B����ł����������͂���܂���ł����B�F�ɔ���Ō}�����A�܂��o���̂������Ă��܂��B |
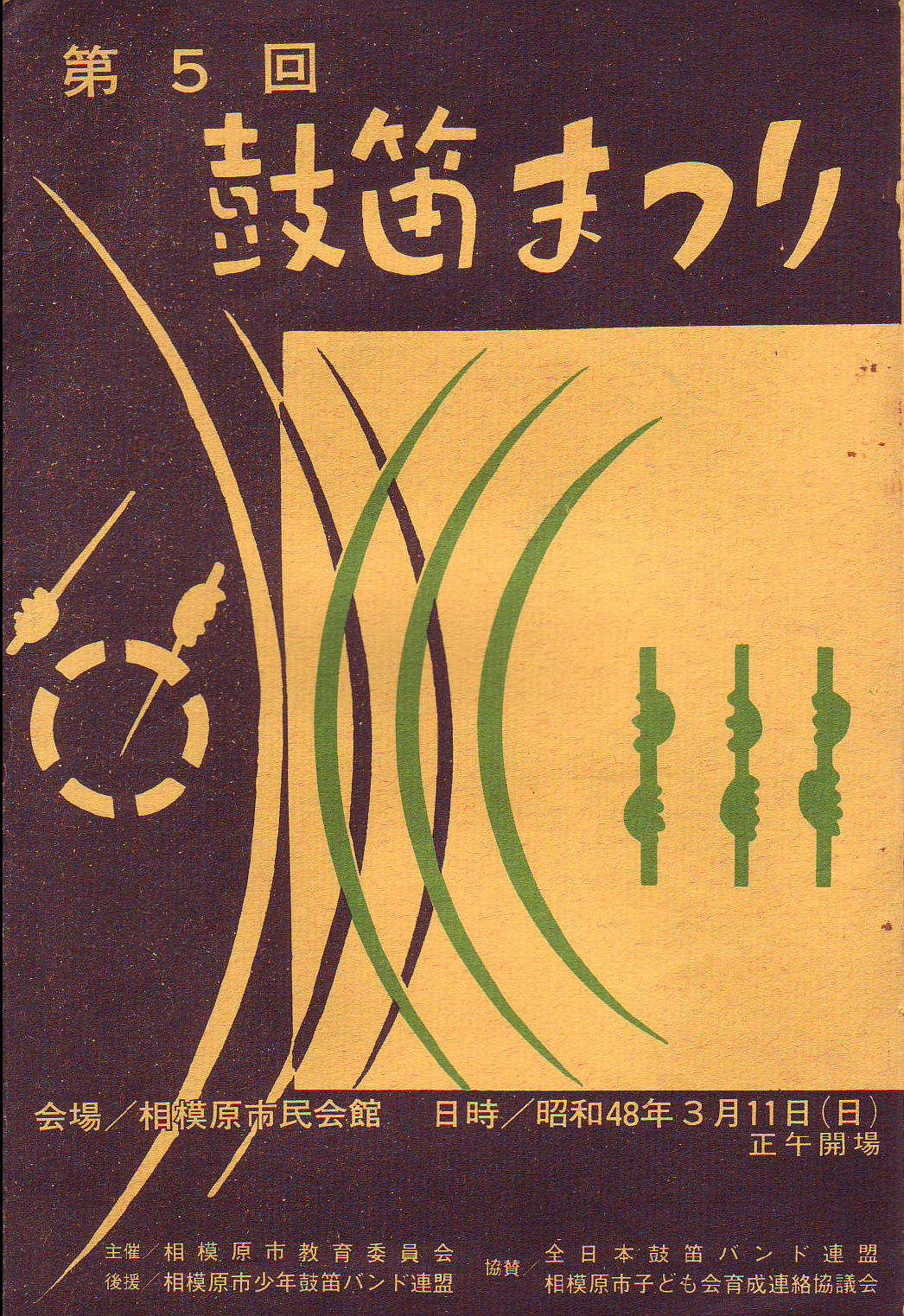 �ۓJ�Ղ�̃p���t���b�g   ���z�ۓJ�� |
 ���a40�N�����̌ۓJ���i�u�������̂̂���݁v���j |
|
 �a�J���q�����N�̘b �a�J���q�����N�̘b |
 �̂̈����w�Z�i�u���͌��s���̎ʐ^���v���j |
| �@ �@���͌��͐펞���A�����≡�l�Ȃǂ���a�J���Ă����q�ǂ���������������e�ʂ̉ƂȂǂɑ؍݂��Ċw�Z�ɒʂ��Ă��Ă��܂����B�c������́A����ȑa�J�����̒��œ��ɖY����Ȃ������N�̂��Ƃ�����Ă��������܂����B �@�����̉�������a�J���ė��������q�Œ����N�Ƃ������킢���j�̎q�����܂����B�����A���ڂ͌����Ȃ�����ǁA�e�ƈꏏ�ɑa�J���Ă��Ă��Ȃ��q�́A�y�j����j�͉ƂɋA���Ă͂����Ȃ��K��ɂȂ��Ă��܂����B�y�j�ɂȂ�ƁA�����N�̓g���g���Ƒ���@���Ă��܂����B���́u������v�ƌ����Ȃ��Ēm���U�肵�Ă��܂����B�ɂ��ɂ����Ƃ�����A���ʼnƂA���Ă����܂����B �����̎��Ƃ���A�������j���̒��ɂȂ�ƁA�u�搶��ԍŏ��ɗ����B��ԑ��������B�v�ƌ����ĕ������ė��܂����B�u���͂悤�B�肪�₽���ˁv�Ƃ������߂Ă�����肵�܂����B���a20�N3��10��(�y)�̓������P�������Ĉȗ��A�����N�͋A���ė��܂���ł����B���킢���q�łˁB���̎��A�A���Ȃ���Ηǂ������Ƃ����Ԃ�݂܂����B�����N��5�N���ŖS���Ȃ�܂����̂ŁA���Ǝʐ^������܂���B����ł����̎q�̊�͖Y����܂���B���v���Ă��������߂������炢�ł��B |
 ���ڂ�b ���ڂ�b |
|
| �@���Ƃ́A�����q��l���̋߂����b�B�X���̖k�ŐV���Ƃ����Ƃ���B���̋������������q�̋߂��ŁA�̂͑�S����������܂����B �@�Z�Ƃ�5�ȏタ�������̂Ŋw�Z�����������A�Z��ł��N������Ă����̂ő���ɂ�����܂���ł����B�����ɋA���Ă��A��������Ȃ���ł��B���ɕ�̎��Ƃ�����܂����B����������������Ƃ���ł͖ʔ����Ȃ��ł��傤�B�܂��ɏ��̎q�̗F�B�����Ȃ�������ł��B �@����⏰���ŁA�͂��ݏ�����������A�c�N�N���u�Ȃ������Ă���܂����B����̂������u�m�q���������Ă����Łv�B���S������ł́A�~�ɂȂ�Ƃ����ł��܂������Ă��āA���ӂ��āA�u�����������傤�Ԃ���v�Ƃ������ēn���Ă���܂����B���傤�����������܂����B������̍b�B�X���̂͂������ō��̂����Ă��܂����B�݂�ȖZ�����Ă��ǂ��Ƃ��A�����܂���ł����B�։����������܂����B�傫�ȃr���̒��ɓ����Ă�����A�l�p�̃r���ɓ���ďĒ��Ђ��ɂ��Ă��܂����B���b�B�X���ɂ́A����Ȃ��X������܂����B |
 |