

![]() 秋の彩り
秋の彩り
| 今月の語り部は、相模原1丁目にお住まいの関口武雄さんです。 殆どの家が自給自足の小麦を粉に挽いて、手打ちうどんを作っていたそうです。ご飯は陸稲3割、麦7割のぼそぼそしたものでした。子どもの頃は、里山や川、屋敷にある木の実を取ることはかっこうの遊びでもありました。人の屋敷になっていた木の実を棒でつついたり、石を投げて落として食べてしまうことがありました。学校は小学校2年生までは宮下の旭小第2分校で、3年生からは橋本の旭小まで1里の山道を歩いて通いました。その通学路で野山の木の実などあさって食べ歩いた懐かしいむかしのお話です。 |
 関口武雄さん |
||
 栗  よそぞ |
栗 近くの里山や東京都の山に栗がありました。山にある自然の山栗で、小粒だが甘くて美味しかったそうです。9月の終わりころ、みんな集まって栗拾いに行っていたとおっしゃっていました。向陽小ができる以前は山林で、そこで栗やきのこを採っていました。(栗の写真) よそぞ よそぞは10月ころ、赤い小さな実が掌の大きさに散らしたようになります。こんな実のかたまりがいくつもあって、まるで花が咲いたようでした。赤い実は米粒ほどの大きさで、もいで食べました。口に入れるとすっぱくて美味しいものではありませんでした。その上、種が大きく、殆ど食べる果肉はありませんでした。見た目が美しくて生け花などにも使われることがあります。 川ぐるみ くるみは川ぶちにあり、種が運ばれて、川ぶちで発芽したものと思われます。黄緑色で一粒が4〜5cmあり、数個がひと房になってぶら下がっています。竹竿の先に鉤をつけて、くるみの房に引っ掛けて落としました。土の中に埋め、皮を腐らせて中の実を取り出しました。硬い皮ぐるみは焙烙で炒ると硬い殻がが割れ、中身を取り出して食べました。油が強く、抜き出したくるみを布に包んで、木部を磨くとつやが出て木目が蘇りました。取り出した実をすり鉢で擂ってペースト状にし、お餅などにつけて、観光地で売っています。今でも毎年取ってきて食べているそうですが、自然食品であり、健康食品でもあります。 |
| きのこ狩り |
||
|
ウナギ |
境川の魚 境川にはハヤ(本バヤ、ニガッパヤ)、ズガニ(毛ガニ)、ウナギ、ヤツメウナギ、ナマズなどがいました。東京都の田んぼの小川には、ババッコ、どじょう、金鮒、銀鮒、カワニナなどが住んでいました。しかし、子どもには煮付けて食用にするほどには取れず、遊びで魚とりをする程度でした。ウナギやナマズは常盤から登って山を越え、小山田の小川やたんぼまで取りに行きました。もめん針の真中を糸で縛り、その上にミミズをすっぽりかぶせて、川岸の空洞になったところに仕掛けました。殆ど釣れませんでしたが、かかると、針は引っ張られて直角になり、ウナギの腹を刺してしまうので逃げられません。ズガニは毛ガニのことで、手を握ったくらいの大きさでした。ババッコはナマズを小さくしたような魚でした。金鮒、銀鮒はタナゴできれいな魚でした。 |
|
| ほんとの話 |
|
| 「こおろぎ」 風呂場は屋外にあり、薪をたいて湯を沸かしていました。風呂窯をたきながらこおろぎを焼いて食べました。こおろぎを針金に通して焼いたり、灰の中に入れて焼いて食べることもありました。こうばしく美味しいものでした。川崎水道のトンネルを掘った時、湧き水を流すために下水を掘りました。地下の赤土が掘り出され、そこに大量のこおろぎがいたそうです。 「赤がえる」 体に赤みがあり、体長10cmほどで川や田んぼにいました。皮をむいて焼いて食べました。鶏肉のような味がしました。 いぼがえるは体長20cmもある大きなかえるで、背中にいぼがあり、押すとそこから白い液を放出しました。食べたことはありませんが、夜に出没して蚕を食べました。 「シマヘビ」 この辺にはシマヘビ、アオダイショウ、ヤマカガシなどがいましたが、シマヘビは、皮をむき焼いて食べていました。 「鉄砲虫」 立ち枯れになった松や栗の大木を切り出し、薪にすると割った所に、穴があり、そこに鉄砲虫が入っていました。鉄砲虫は白い幼虫で体長が3〜5cmもありました。取り出して焼いて食べました。香ばしい味がしました。 「蜂の子」 あしなが蜂の巣を見つけると、蜂を追い払い、蜂の巣を横取りして、巣から幼虫を取り出して焼いて食べました。蜂は香ばしく美味しいが、刺されると大変なので、スリルがありました。 |
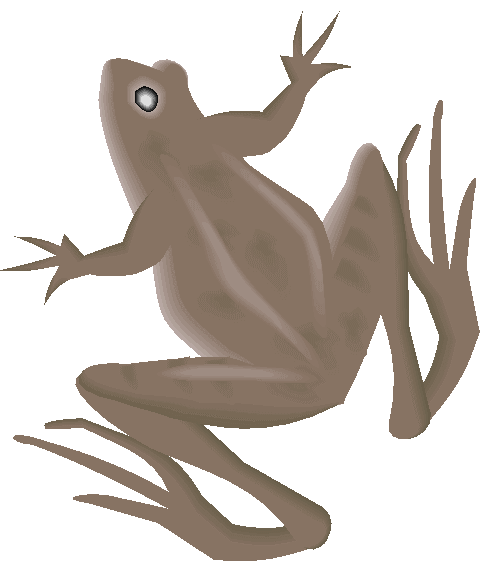 赤がえる |